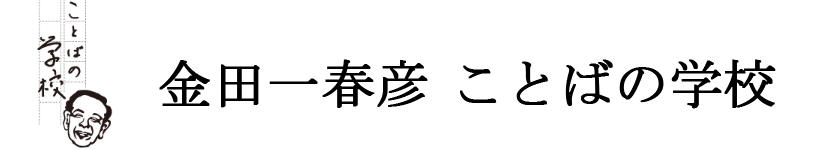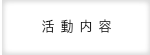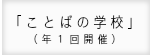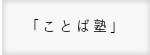第七回 ことばの学校
日 時 平成18年11月11日㈯・12日㈰
会 場 スパティオ小淵沢
参加人員 約200名
テーマ「ことばっておもしろい」
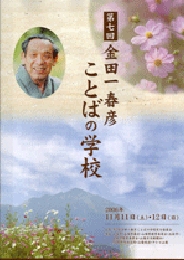
八ヶ岳山ろくの紅葉が一番の見ごろを迎えた11月半ば。
真っ赤なもみじがあたりを彩
る中でことばの学校が開催された。
冷たい雨が降るあいにくの天候だったが、
初日は
TBSのラジオ番組でお馴染みの遠藤泰子さん、
そして2日目は落語界の中堅、三遊
亭楽麻呂さんの出演とあって、
大勢の観客が詰め掛けた
。
♦11月11日♦
■1 開校挨拶、そしてことばの持つ力について 金田一真澄
- 校長として、金田一春彦長男が開校挨拶。続いて今回のことばの学校のテーマである「ことばって面白い」に沿って、ことばのもつ不思議な力について解説した。例えば医者の世界では「プラシーボ」(偽薬)効果と言われるものがある。「これはよく眠れるお薬ですよ」と言われると、たとえそれが単なる小麦粉でも患者は暗示にかかって本当に眠ってしまう。またロシアでは熊という単語を使わない。それを口にしただけで本当に出てきそうな恐怖感があるからだという。戦争中は「玉砕」という美しいことばに惹かれて、何人もの若い兵士が命を落した。あれが「犬死に」と言われたら、どうだっただろうか?ことばが人間におよぼす影響力の強さは、古今東西同じであることなどを1時間にわたって講演した。
24〕
■2 方言川柳表彰式
- 今回のお題は「山」。
- 山と言えば八ヶ岳を思い起こすが、住む場所が違えばふるさとの山は違ってくる。山はいわばふるさとへの思いでもある。住み慣れた故郷への思いが、山という題を借りて5、7、5の短い川柳にこめられている、と選者の一人、中沢久仁夫先生の講評も行われた。
24〕
■3 講演 遠藤泰子
- TBSラジオで「森本毅郎スタンバイ」や「永六輔の誰かとどこかで」で良き女房役として活躍する遠藤泰子さん。長年アナウンサーとして活躍してきたが、その影にはつらい経験もあった。でも彼女をいつも支えたのは「ことばのもつ温かい力」。
- ことばは使い方を間違えれば刃物にもなるが、反面また人の心を開く優しい力をもつ。自分は他の人のことばの力で励まされながら生きてきたが、自分もまた他の人をいやす力になれたらと語る。
24〕
♦11月12日♦
■1 朗読 八ヶ岳朗読サークルほがらか
- 金田一春彦著作の中から「父京助を語る」「日本語を反省してみませんか」「心にしまっておきたい日本語」などを朗読。「童謡、唱歌の世界」では、野口雨情の「赤い靴」をとりあげ、この童謡が生まれた背景などを春彦独自の視点で解説した文章を朗読。また合間には藤森義昭氏の伴奏で「十五夜お月さん」などを実際に歌ってきかせた。
24〕
■2 甲州民話 茅野頼母 小林是鋼
- 甲州に古くから伝わる民話を語り伝えている茅野頼母さんに、今回は「がんまくさん」を語ってもらった。「がんまくさん」とは力が強くて頑固な男のこと。倒れた鳥居を一人で立ててしまうような力
- 持ちが、土地の人たちのために力をつくすお話。
- この後、小林是綱さんが、「がんまくさん」の中で語られた甲州の方言について解説。「子供」を「ぼこ」、「話をしましょう」を「話をしずか」といったこの土地ならではの言い方を説明。またゆっくりとした口調で語られる民話に、私たちが耳を傾ける機会が減ってきたことを惜しみ、「スローライフ」ならぬ「スロートーク」を提案した。
24〕
■3 落語教室 三遊亭楽麻呂 会場にいらした皆さん
- 三遊亭円楽の門下生である楽麻呂さんを講師に招いて、落語教室を開催。
- ただ楽しく聴いている落語だが、実はさまざまな決まりごとがあることを解説。例えば演者にとって必ず上手(かみて)下手(しもて)があり、ご隠居さんがハチ公に話す場合は右から左へ顔を向けて、上手から話を運ぶこと。また扇子の使い方ひとつでお箸になったり、キセルになったりすることを実演した。
- 後半は会場の中から希望者を募って、舞台に上げ、実際に落語をレッスン。戸の叩き方にも若い女性の場合と男の場合では、微妙に音が違うことなどを教え、会場内の爆笑を誘った。
24〕
■4 落語 三遊亭楽麻呂
- 演目は「禁酒番屋」。お殿様が禁酒令を敷いたために、酒好きのお侍さんが大弱り。酒屋の小僧に頼んで、何とか城内に酒を持ち込もうとする。しかし番屋にはうるさい番兵が控えていて、「お菓子です」とごまかして持ち込もうとする酒屋の小僧から酒を取り上げてしまう。そこで考え付いたたくらみは……?
- 今回は落語開催ということで、会場内も特別に座布団を敷いてお座敷風に。即席の高座の雰囲気を楽しみながら、偉ぶった侍、町人の主人、小僧などさまざまな登場人物の声や個性を表現する落語の面白さにひたった。
24〕
■5 修了式
- 春彦の妻金田一玉江、長男真澄、長女田中美奈子から、受講した一人ひとりに修了証を手渡し。「来年もお元気でお目にかかりましょう」と玉江が挨拶をした。