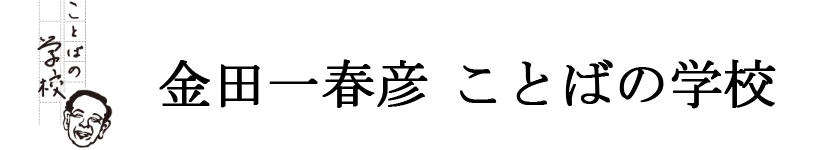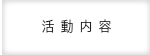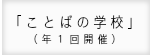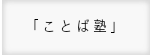第一回 ことばの学校
日 時 平成12年11月23日・24日
会 場 入学式オープニングセミナー
…八ヶ岳ロイヤルホテル
大泉分校…谷桜コミュニテイホール
- 高根分校…北甲斐亭
- 小淵沢分校…えほん村
- 長坂分校…清光寺
参加人員 約200名

平成10年7月に、旧八ヶ岳大泉図書館に金田一春彦先生が
蔵書2万冊余りを寄贈し、「金田一春彦ことばの資料館」が誕生した。
貴重な蔵書や資料のほか「日本の方言コーナー」が設けられ、
地域に親しまれ地域の文化を発信していく
方言の魅力が
紹介・解説されている。
この「八ヶ岳高原ことばの学校」は「ことばの資料館」を母体として、日本語のすばらしさを語り、貴重な方言を見直し、
ことばの魅力を通して地域文化を発展させていこうと
春彦先生を校長に迎えてスタートした。
“芸術と語ることばのふれあい2000年シアター”が
八ヶ岳南麓の高原の秋を彩った。
■1 開校式挨拶 金田一春彦
- 87歳となった先生は、「このような言葉についての勉強の機会ができたことは本当に嬉しい、しかも学会ではなく、一般の人も参加する研究会がよいと思うが、 それがここ山梨県にできたことの値打ちが高い」と壇上でゆったりと語った。
- 方言学者の説は大きく二つに分かれるとして、一つは、江戸時代以来の区分で、東日本と西日本に分ける説(東日本とは愛知県と福井県とを結ぶ線から東側を指し、西日本とはその西側つまり近畿・若狭以西)と、もう一つは都から近いか遠いかという区分である、と日本地図を指し示
- しながら説明。都に近い中央の方が新しいと思われがちだが必ずしもそうではなく、むしろ田舎の方がどんどん言葉を変えて新しくしていると述べ、山梨県は東日本に属するが、西日本の言葉もどんどん入ってくるし、新しい言葉へと流れていく地域であるので、言葉の研究の一番いいポイントにある県の一つである、と熱意をこめて「ことばの学校」への期待を語った。
■2 語り「八右衛門湧水」 梅津幸三
- 「言葉は、その地域の生活そのもの。生きることそのものが最高の美。怒り、悲しみ、喜び。民話はその地域の暮らしの中から生まれたもの。その生活のすべてを包み込んでいるものだとすれば、その中の人間の苦悩も含めて、生きる美しさがなければならない」という梅津幸三さんの、地元大泉に伝わる民話「八右衛門湧水」の語り。
■3 トークショー 角野栄子 木村裕一 工藤直子
- 「ことばの文化」をテーマとするトークショーで、「魔女の宅急便」の作者角野栄子さん、「あらしのよるに」の作者木村裕一さん、「あいたくて」などの詩の作者工藤直子さんが出演。作品を作っていく時の自分のこだわりや癖など、ことばとの長い付き合いから生まれてきたことばへの思いを披露。角野さんは「声に出してことばを読みながら書く。音の響きが大切」と軽やかに、木村さんは「ことばが人の心を揺らし身体的反応まで起こさせる不思議さ」を、そして工藤さんは「ことばの意味や音の響き、文字の形など、どれをとっても面白い」と、それぞれ朗読なども交えながら語り合った。
- 24〕
■4 大泉分校 会場:谷桜コミュニテイホール
- 「文化の村がふるさとを語る」と題して、甲州弁による民話が河野司さんの朗読によって語られた。「八ヶ岳と富士山」「甲斐の湖」「笛吹権三郎」「長右衛門とむじな」の話が、表情豊かに語られ、大久保みゆきさんの篠笛演奏も興を添えた。
- 「八ヶ岳と富士山」の話は図書館ボランティア団体のYOMUTOMOも自作の紙芝居で熱演した。
■5 高根分校 会場:北甲斐亭
- 「風祭りの夜-風の三郎社-」~幻の賢治をたずねて~と題しての宮沢賢治作品の朗読とお話。朗読は坂本和子さん、お話は保坂庸夫さん。
- 賢治が岩手県の盛岡高等農林学校にいた時の親友だった保坂嘉内が韮崎市の出身であったことから賢治の作品に山梨県の風物が陰に陽に影響を与えているのではないかと言われていることについての興味深いお話があった。
■6 小淵沢分校 会場:えほん村
- 「こどもとことば」というテーマで角野栄子さんと木村裕一さんのお二人が対談。児童文学を巡って、お二人がどのようなお話の作り方をするか、また絵本作家になったきっかけなど話され、作者の側からのコメントが、多くの子どもたちをも含めて読者側の聞き手たちを魅了した。
■7 長坂分校 会場:清光寺
- 「ことばのいのち」~お寺でポエム~と題して工藤直子さんがご自身の詩「のはらうた」を解説・鑑賞した。持ち前の飾らない素直さで語りかけて、生き生きとしたことばのいのちを感じさせてくれた。
■8 民話を訪ねてウォーキング
- 2日目の午前10時より、3コースに分かれてのウォーキングとなった。民話や歴史を尋ねてそれぞれのコースで八ヶ岳高原の魅力発見!
- 1)天女山コース
- 2)八右衛門コース
- 3)風の三郎社コース
■9 芝居「雪娘」 劇団やまなみ
- 観客の心に響くことばを大切にして、地域に根ざした公演活動を45年間続けてきている劇団やまなみ。役者の演技が観客の気持ちと一つになった時の大きな感動を創り出すために、人間像についてつぶさに分析をするという。そんな歴史を感じさせてくれる舞台だった。
■10 日本語オペラ民話「あまんじゃくとうりこひめ」
- 台本…若林一郎 作曲…林 光
- 出演…オペラ家藤本紳二ほか峡北在住オペラ愛好会
- オペラ愛好家たちが日本の民話を舞台に登場させてくれた。元オペラ小劇場こんにゃく座制作部、舞台監督の藤本紳二氏の創作演出によるユニークなオペラ。日本語が美しく響いた舞台であった。
■11 修了式 会場:大泉村民体育館
- 芝居とオペラの行われた同じ会場で午後3時20分より行われた。金田一春彦校長は壇上ではなく、舞台下で親しく参加者に修了証書を手渡された。バラエティに富んだ第1回「ことばの学校」の夢の響宴もここに幕を閉じた。